blog
家づくり|火災警報器の設置
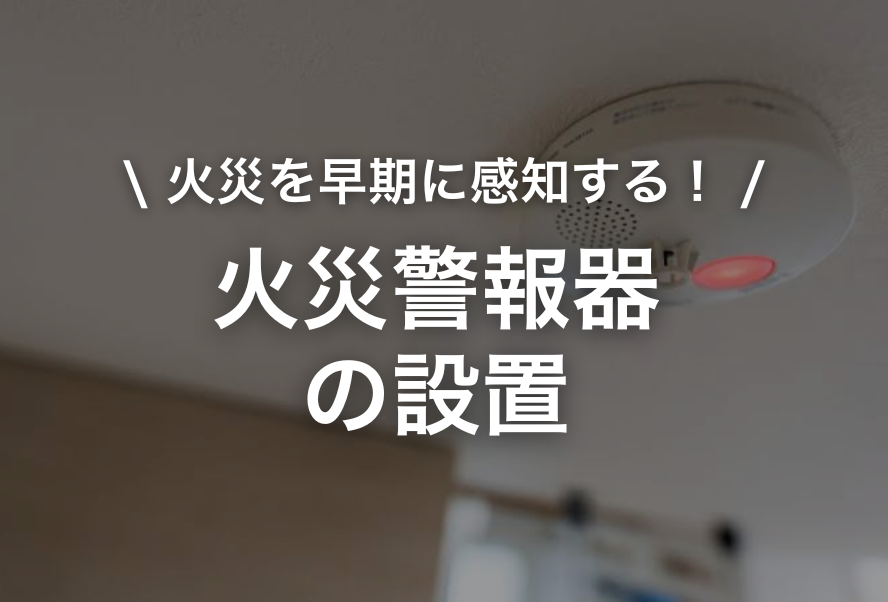
火災時の安全のために
火災警報器とは、早期に感知して警報音や音声で知らせる機器です。現在では、既存住宅も含めてすべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。
火災警報器の種類
住宅用火災警報器には、「煙」を感知するものと、「熱」を感知するものがあります。火災発生時には、煙のほうが早く広がることが多く、法律では原則として「煙」を感知するものの設置が義務付けられています。台所など、日常的に煙や水蒸気が滞留しやすい場所には熱感知式が適しています。
電源方式別では、家庭用電源で使えるAC100V式と、電池式があります。AC100V式は電気配線工事やコンセントが必要ですが、電池交換が不要です。電池式でも、寿命が5~10年と長いリチウム電池を使ったものもあります。
火災を感知した警報器だけが鳴る単独型と、設置されているすべての警報器が鳴る連動型があります。連動型は、ほかの部屋にいても気が付くのでより有効だといえるでしょう。
選択の際、ひとつの目安となるのがNSマークです。日本消防検定協会の検査に合格した製品に表示され、住宅用火災警報器としての品質を保証します。
設置の種類
設置場所は、寝室(主寝室や子ども部屋)と階段です。3階建て以上の場合、寝室から2階離れた階の階段にも設置します。寝室がない階でも、床面積7㎡以上の居室が5部屋以上ある場合は廊下に設置します。
台所などそれ以外の場所への設置基準を設ける市町村もあるので、必ず所轄消防庁で確認しましょう。
取り付け位置
■天井に設置する場合
✔警報器の中心を壁から0.6m(※)以上離して取り付ける
✔梁などがある場合は、それらから0.6m以上離して取り付ける
✔エアコンなどの吹き出し口がある場合は、吹き出し口から1.5m以上離して取り付ける
※熱を感知するものは0.4m以上離して取り付ける
■壁に設置する場合
✔警報器の中心が天井から0.15~0.5m以内の位置になるように取り付ける
まとめ
いかがでしたか?火災が発生したときは、目で煙や炎を見たり、鼻で焦げ臭いにおいを感じたり、耳でパチパチという音を感じたり、、、と五感によって気づくことがほとんどだと思います。しかし、それだけでは、就寝中や仕切られた部屋などにいた時などは、火災に気づくのが遅れてしまいます。
だからこそ、火災の発生をいち早くキャッチし知らせてくれる火災警報器を設置し、火災時の身の安全を図るようにしましょう。

