blog
家づくり|保管書類と保険の加入
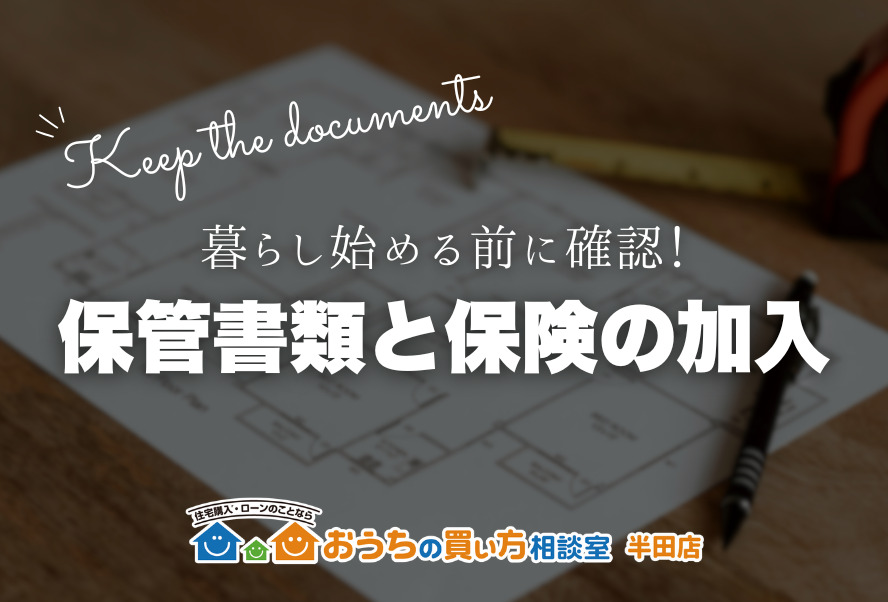
検査と必要書類
待ちに待った新しいわが家が、いよいよ完成しました。さっそく引っ越したい気持ちは分かりますが、その前に、暮らし始めてからのトラブルを極力回避するため、確認しておくことがあります。
完了検査
建物が完成した時に、その建物が法律に適合しているかどうかを調べる検査のことです。
実際には、設計者など工事監理者が確認検査機関に完了検査申請書を提出し、建築主事または指定確認検査機関が検査して建物が建築基準法と関連規定に適合しているか、確認申請内容と相違なくできあがっているかを確かめて、適合していれば建て主に検査済証が交付されます。
竣工検査
完成後、建物が図面や打ち合わせ通りにできあがっているかを確認する検査が、竣工検査です。建て主、施工者、設計者など工事監理者、場合によっては機器類の納入業者などが立ち会います。
この検査は、目で見ることのできる仕上げの具合や、建具類の開閉状況、設備機器類の点検や操作指導が中心で、壁の内部など隠れて見えなくなっている部分は、工事中にチェックが済んでいることが前提です。手直しの必要が明らかになった部分は、引き渡しまでに補修工事を済ませておきます。この検査で見つからなかった不良箇所でも、主要構造部にかかわるもので、竣工の時にすでに生じていたと判断されるものは、品確法により竣工後10年間に発見されれば、補修してもらうことが可能です。
引き渡し
補修工事の終了を確認したうえで、出入口の鍵や引渡証明書などの関連書類を受け取り、建物の引き渡しを受けます。
登記
引き渡し、電気やガス・水道などの手続きとともに、登記の手続きを進める必要があります。
まずは1ヶ月以内に建物の表題登記の手続きをします。次に保存登記、そして登記済証(権利証)の交付を受けます。金融機関からの融資を受けた場合は、これに抵当権の設定登記が続きます。いずれも専門的な知識が必要なので、表題登記は土地家屋調査士に、保存・抵当権設定登記は司法書士に手続きを依頼する場合がほとんどです。
保管しておく書類
役所または民間確認検査機関など
・建築確認申請書…建物の計画時に建築基準法等に適合するものかどうか、建築主事の確認を受けた申請書
・検査済証…建物の工事が完了したときに、検査機関へ完了検査申請書を申請しなければならない。完了検査申請書の提出後、係員により現地での完了検査が行われ、建築基準関連規定に適合していることが確かめられた場合に交付される
・昇降機用検査済証…ホームエレベーターを設置した場合に、建物とは別に必要
・設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書…住宅性能表示制度を利用し、設計住宅性能評価や建設住宅性能評価を受けた場合
・長期優良住宅認定証…長期優良住宅認定を受けた場合、書類図面を併せて
工事施工者
・建築工事完了引渡証明書…施工会社がどういう建物をいつ建て、それをいつ建て主に引き渡したかが書かれた書類
・各種証明書…工事施工者の印鑑証明書や資格証明書等
・瑕疵担保責任保険証明書…保険に契約していることを証明するもの
・各種設備機器の保証書および説明書…給湯器のリモコン、キッチンの機器類、トイレの洗浄便座等
・工事施工写真…基礎工事や断熱材、仕上げ工事などの施工写真
設計者
・監理業務完了通知書…工事監理業務の完了の報告
・竣工写真(施工者の場合もある)…完了建物の内外部の写真
・竣工図…工事中に発生した設計変更などを図面上でも修正し、竣工した建物を正確に表した図面
住まいの保険
火災保険、住宅総合保険
もらい火による火災は、火元の住人から補償を得ることができないため、自分で火災保険に加入しておくことが肝心です。
火災保険は、鉄筋コンクリート造や耐火被覆した鉄骨造の場合に保険料が安くなりますが、木造でも屋根・外壁・軒裏・天井・壁の室内に面する部分が、防火性のあるつくり(省令準耐火構造)となっていれば、火災に強い建物の扱いとなり、保険料が下がります。また、たいていの火災保険は、落雷や風災による損害も補償します。
住宅総合保険は、物体の落下・衝突・水漏れ・盗難・水災などによって生じた損害も補償します。
家財保険
火災保険の多くは、対象を建物に限っており、家財や現金は補償していません。火災、台風などによる家財の汚損や、盗難の被害に対しては、別に家財保険に加入します。家財保険は、火災に限らず日常の偶然の事故、汚損などの原状回復費用などが基本的に含まれています。
地震保険
火災保険では通常、地震によって起きた火事で建物や家財が焼けても保険金は支払われません。地震、火山噴火、それに伴う津波などによって起こる火災、家屋の損壊、流出、埋没に備えるには地震保険に加入する必要があります。
住まいの保険の決め方
①建物の物件種別を確認(住宅か、併用か)
②建物の構造(木造か、非木造か)・面積の確認
③建設費をもとに保険会社と加入者が協議のうえ、保険金額を決める
④家財保険への加入・非加入の選択
⑤地震保険への加入・非加入の選択
⑥各保険会社の商品を比較検討し、付帯する特約などを選択
⑦保険期間を決め、保険会社に保険料を算出してもらう
⑧契約(保険料は一括または分割で支払う)

