blog
家づくり|住宅を彩る外装材
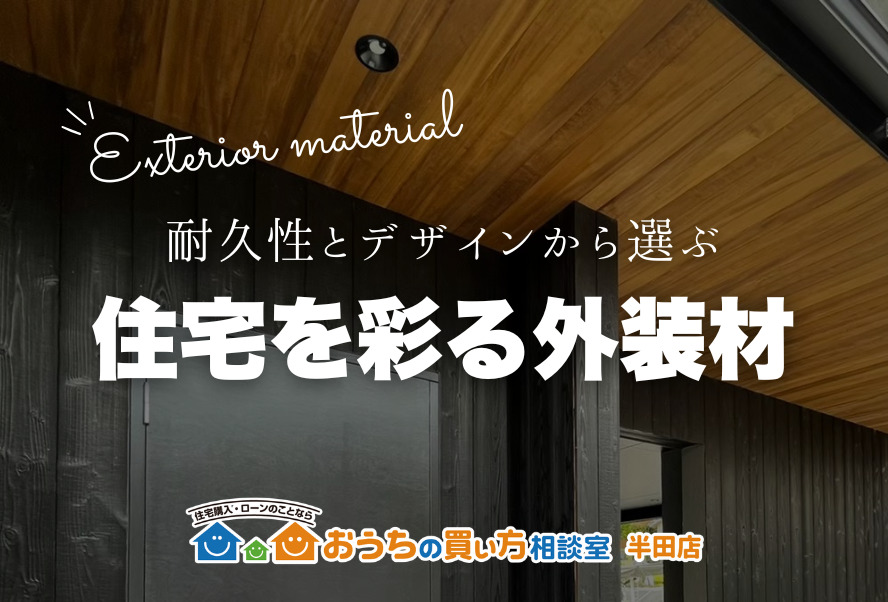
デザインと性能
外壁材とは、建物の外側の仕上げ材のことで、外壁材と屋根材があります。風雨や紫外線から住宅を守るとともに、建物の外観や街並みにも影響を与えます。
そのため、耐久性とデザインの両面から選ぶ必要があります。
外壁材の種類
外壁材には、乾式工法のサイディングと、湿式工法の左官壁、タイル、レンガ、石などがあります。専用金具を使って留め付けるサイディングは施工が簡単で工期が短いため、近年多くの住宅で採用されています。
セメントと砂を混ぜ、水を加えて練ったものをモルタルといい、これを練りつけた壁はモルタル壁と呼ばれています。サイディングはモルタル壁より軽いため、建物に大きな負担をかけないというメリットがありますが、湿式工法の左官壁は表現力が高く、個性的な外観が実現できることから見直されています。
代表的な外壁材とその特徴
乾式工法
■窯業系サイディング
・材質…セメントやケイ酸カルシウムの原料に繊維質材料を混ぜ、成形硬化させたもの
・特徴…安価で耐久性・耐火性があり、デザインのバリエーションも豊富。厚さは、釘打ちで容易に施工できる14mmと、質感が高い15mm以上がある。最近の製品は塗膜の耐久性が向上しており、セルフクリーニング機能を付加したタイプもある
■金属系サイディング
・材質…表面の金属板と芯材に断熱材や遮音材を組み合わせたもの
・特徴…ほかの外壁材より軽く、建物に負荷をかけにくい。シャープでモダンなデザインで人気が高まっている。錆に弱い鋼板の弱点を克服し、特殊なメッキで耐久性を高めたガルバリウム鋼板を使ったものが増えている
■木質系サイディング
・材質…無垢の木材や合板など、木質系材料の板を用いるもの
・特徴…木の温かみのある表情が楽しめる。無垢のものは、スギやウエスタンレッドシダーなど耐水性の高い樹種の板を張る。縦張りと横張りがあり、建物の下から重ねながら張っていく下見板張りが代表的。木材を保護するための塗装が不可欠で、定期的な再塗装で寿命を延ばすことができる。木材を外装に使用する場合には防火上の制限があり、不燃処理されたものを使う
■セラミック系乾式サイディング
・材質…粘土を焼成させたタイルを用いるもの
・特徴…高い質感と耐候性が最大の魅力。紫外線による色あせがほとんどなく、基本的に塗り替えを必要としないため、メンテナンス費用を削減できる
湿式工法
■塗り壁
・材質…モルタル壁を下地に左官材を塗るか、塗料を吹き付けて仕上げたもの
・特徴…表現力が高く、サイディングと違って曲面への塗布も得意なことから、個性的な外観を実現できる。日本の伝統的な壁仕上げの漆喰壁も塗り壁である
■タイル・レンガ・石
・材質…モルタル下地の上にタイルやレンガ、石を張って仕上げたもの
・特徴…素材感あふれる外観を演出できる。施工性を高めると同時に剝離を防止するため、接着剤や金具で固定する方法もある
その他
■ALCパネル
・材質…軽量気泡コンクリートに鉄筋を入れたもの
・特徴…パネル内部に多くの気泡が含まれることから、通常のコンクリートの4分の1と軽く、高い断熱性を持っている。耐火性に優れ、防火地域、準防火地域の外壁材として適している
屋根材の種類
屋根は風雨や直射日光など過酷な条件にさらされる部分ですから、耐久性の高い材料が使われています。また、防水性では屋根の形状も大きくかかわってきます。
スレート
本来は粘板岩を薄く剝いだものをスレートと呼びますが、現在ではセメントを繊維質材料で強化した人工スレートが大半となりました。安価で軽量なことから、多くの住宅で採用されています。塗り直しの手間を軽減するため、塗装の耐久性を大幅に高めた製品が発売されています。人工スレートと区別するため、石のスレートを天然スレートと呼びます。耐久性が高く、天然石ならではの素材感があります。
金属
銅やアルミ合板、トタン、ガルバリウム鋼板などの金属板を屋根材としたものです。軽量で建物に負担をかけず、勾配が緩い屋根にも葺くことができます。加工しやすいため、複雑な形の屋根でも容易に対応できます。
近年、価格と性能面からガルバリウム鋼板が増えています。平葺きが一般的ですが、瓦の形にした金属瓦もあります。最近、太陽光発電システム一体化も出ており、後載せタイプよりも見た目がすっきりします。
瓦
粘土を焼成して作られた瓦は、堅牢で重厚感あふれる代表的な屋根材です。耐久性が高く、メンテナンスの手間がかかりません。釉薬(ゆうやく、うわぐすり。素焼きの陶磁器の表面に塗る薬品。焼成によってガラス質となり、強度の向上や防汚などの役割をもつ)を塗布して焼いた釉薬瓦が一般的ですが、無釉瓦もあります。大きく分けて和瓦と洋瓦があり、数多くの形状があります。粘土瓦のほかに、セメント瓦もあります。
主な屋根の形
切妻屋根
屋根の原型ともいわれ、代表的な屋根の形。多様な形態が可能。防水面の弱点が少ない
片流れ屋根
最もシンプルで経済的な屋根。特殊な部分が少ない分、防水性も高くなる
寄棟屋根
代表的な形状の1つ。建物の4周に軒が回るため、外壁の保護に有利。工事費は切妻よりも割高。妻壁がないため、小屋裏換気がとりにくい
方形屋根
寄棟屋根の1種で、正方形プランに用いる
入母屋屋根
上部に切妻、下部に寄棟を組み合わせた形状。日本特有で社寺建築などでみられる
ヴォールト屋根
曲面の屋根。個性的な外観が可能。施工難度が高く、工事費もかかる。屋根材も限られる

