blog
家づくり|床下・小屋裏の湿気対策
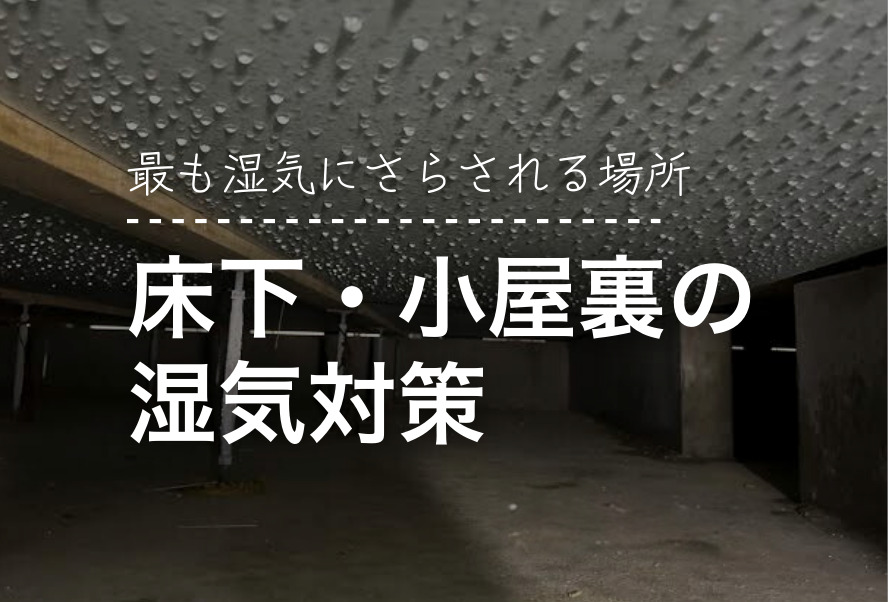
湿気を防ぐには
現代の家のつくりは、昔に比べて湿気がこもりやすくなっています。湿気は木材を傷めるばかりでなく、土台にも影響を与えます。今回は、湿気を防ぐにはどうしたらよいのかを見ていきましょう。
床下の湿気は大敵
前回で防蟻・防腐の要は「水」の扱いにあると述べました。シロアリや腐朽菌・カビの被害のほとんどが床下から始まるのは、床下が最も浸水や湿気にさらされるからです。建物に作用する水分・湿気のうち、生活用水の水漏れと地面からの湿気は、いずれも床下に表れます。
また、結露水は窓や壁に付くものと思われがちですが、床下に用いた補強金物に発生する結露水も、実は土台を傷める原因になっています。
床下を防湿仕様に
昔の家では、内風呂や床下の配管もなく、気密性も低いので結露もありませんでした。土壌からの湿気はあったものの、コンクリート基礎ではなく高床だったため、床下が開放されている状態で、湿気がこもらないつくりでした。この点において現代の家は、湿気を防ぐには不利なつくりといえます。
特に水まわりが集中する家の北側は、日当たりが悪く乾燥しにくいので、湿気が集まりやすい部分です。密集した住宅地などでは隣家との距離が近く、ブロックなど通風が期待できない塀が迫っていると、基礎に換気口を設けていても思うように湿気が出ていかない状態も見られます。積極的に防湿の措置をとっておく必要があります。
調湿材を置くなど建築後に行える対策もありますが、設計段階で検討しておくべきことがほとんどです。そして、暮らし始めてから床下材や配管の点検が容易に行えるよう、床下点検口を適所に設けておく必要があります。
小屋裏にも換気が必要
小屋裏とは、屋根と天井の間にある空間のことをいいます。この部分の空気はたいていの場合よく乾いていて、木材を腐らせることは少ないのですが、建物には必ず小屋裏換気口が設けられています。
その理由は2つあります。1つ目は、夏の小屋裏温度上昇の緩和です。屋根面に受けた熱射は、そのまま小屋裏に伝わり、相当な高温になります。この熱を換気口から逃がし、小屋裏の温度を外気温程度に下げます。
2つ目は、冬の結露防止です。暖房した室内の温かく湿った空気が小屋裏に流れ込むと、冷えた空気に触れ結露を起こすことがあります。これを早く乾かすことと、外気温に近づけることで屋根材の裏面の結露を防止します。
また、万が一屋根に雨漏りが起こったときに、濡れた小屋裏の部材が長く湿ったままになるのを防ぎます。
床下と同様、小屋裏も点検が行えるよう、天井からの出入口を確保しておく必要があります。
まとめ
いかがでしたか?床下は建物を健康に維持するための基盤となる空間です。湿気の管理や通気性の確保など、床下のメンテナンスをしっかりと行っていくことがとても重要です。

