blog
家づくり|地震保険で震災に備える
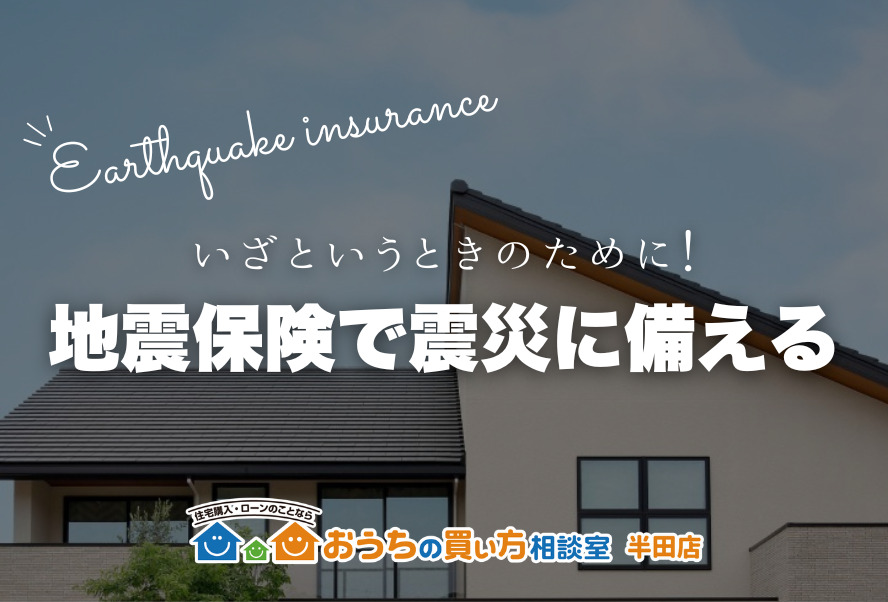
地震保険
いざというときの大地震に備えて、地震による損害を補償してくれる保険に関心を持つ人は多いでしょう。通常の火災保険などでは補償されない地震や津波による侵害に対応するのが地震保険です。
地震保険とは
地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流出による損害を補償する、地震災害専用の保険です。通常の火災保険では、地震によって起きた火事で建物や家財が焼けても保険金は支払われません。住宅建設時に建設業者や宅建業者が加入する住宅瑕疵担保責任保険や、地盤保証会社が加入する地盤保証も、地震や津波などの自然災害による被害は補償対象外です。
こういったことから別に地震専用保険がつくられました。
保険の引き受け先
最も一般的なのが各損保会社の「地震保険」です。他にJA共済の建物更生共済、全労災の自然災害保険付火災共済などの「共済保険」もあります。いずれも火災保険への加入が前提で、地震被害の保険を付帯する形での契約です。それぞれ保険料が安い、補償金額が大きい、掛け捨てでないなど特徴があります。
大きな地震への対処では違いがあります。大地震では保険金が莫大になりすぎて支払われなくなるのではという心配がありますが、地震保険では将来発生する巨大地震に備えて積み立てがされており、また政府が損保会社から再保険を引き受けることで、損害を補償する仕組みになっています。地震保険は、民間の損害保険会社と国が一体となって運営している公益性の高い保険なのです。
これに対し共済は自己資金で運営しており、巨大災害の場合には補償に限度が生じる可能性があります。
SBI少額短期保険株式会社の地震補償保険は、地震保険単独で契約が可能です。ただし、賃貸住宅は契約できず、自己所有でも昭和56年5月以前の建物は原則契約不可など制約があります。1~2年の短期の掛け捨て保険で補償金の上限も低いので、地震保険や共済に上乗せする利用方法と考えるのがよいでしょう。
補償額について
「地震保険」は主契約である火災保険の保険金額に対して建物・家財ともに範囲が決まっており、建物は5000万円、家財は1000万円が限度です。受け取れる補償額は全壊で100%、半壊で30~60%、一部損壊で5%と損害の程度によって違います。そもそも「地震保険」は被災者の生活の安定を目的に創設されたもの。住宅の再建を目的としていないことに注意しましょう。
地震損害の保険と保険金
✅全損…地震保険金額の100%
・建物…地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の50%以上となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延べ床面積の70%以上となった場合
・家財…地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の80%以上となった場合
✅大半損…地震保険金額の60%
・建物…地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の40%以上50%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延べ床面積の50%以上70%未満となった場合
・家財…地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の60%以上80%未満となった場合
✅小半損…地震保険金額の30%
・建物…地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の20%以上40%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延べ床面積の20%以上50%未満となった場合
・家財…地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の30%以上60%未満となった場合
✅一部損…地震保険金額の5%
建物…地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の3%以上20%未満となった場合、または建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmをこえる浸水を受け、建物の損害が全損・大半損・小半損に至らない場合
家財…地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の10%以上30%未満となった場合
地震保険の保険料
保険料は、建物の構造(木造・非木造)によって、都道府県ごとに決められた料率に保険金額をかけて計算されます。建物の耐震性能によって最大30%割引され所得税と住民税の控除対象となります。

